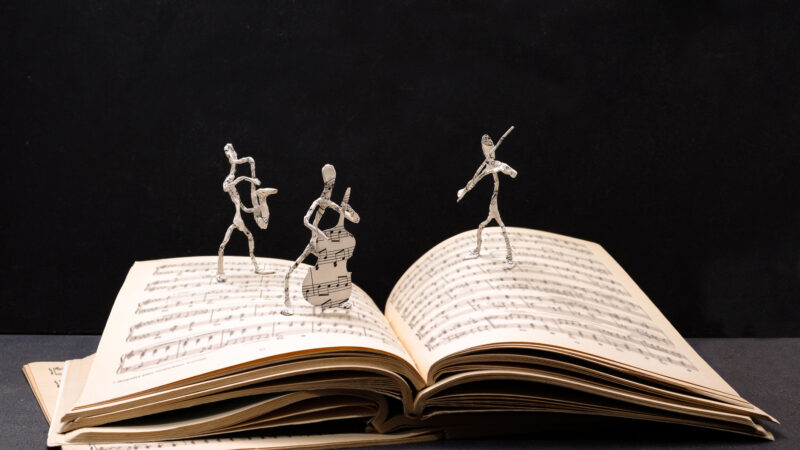脳脊髄液静脈瘻1
2025.08.20
はじめに
脳脊髄液漏出(減少)症の難治例の原因の一つとして「脳脊髄液静脈瘻」があります。
そして、静脈瘻に対する検査および手術が、昨年2024年12月から日本でも行われるようになりました。現時点で、それらを行える医師は日本に一人だけです。
この情報を知ったのは今年の3月。思いがけない経緯からその医師にご縁を繋いでいただき、検査・手術を受けることができました。今回は、この情報を必要とする方の参考になればと思い、この体験を文章に残すことにしました。
脳脊髄液漏出(減少)症とは
まずは、脳脊髄液漏出症がどんな病なのかについて少し触れておきたいと思います。いまだ解明されていな部分が多い病ですので、これから情報が刷新されていくものであることをご承知いただければと思います。
脳脊髄液漏出(減少)症とは、脳や脊髄を包む髄膜の中に流れている髄液が、なんらかの理由で髄膜外に漏れてしまい、脳圧・髄液圧が低下する病です。
通常は髄液の中に浮かんでいる脳が降下し、血管が牽引されるとともに視床下部などの機能が阻害され、激しい頭痛や倦怠感をはじめとする多種多様な症状が現れます。
発症のきっかけは様々で、外傷や手術・麻酔などの医療行為によるものもあれば、原因不明の自然発症もあります。
この病気の概念が日本で知られるようになったのは2003年頃のことで、まだ広く認知されている病気とは言えません。診断に辿り着くまでに時間がかかるケースも少なくありません。
治療の流れ(プロトコル)
この病に対しての治療薬はありません。現時点での海外での一般的な治療方法は、以下の通りです。
・保存的治療法:安静臥床、水分補給
・硬膜外生理食塩水注入(生食パッチ):硬膜外に生理食塩水を注入し、一時的に髄液圧を補う方法です。補助的にも、診断的に利用されることもあります。
・硬膜外ブラッドパッチ(EBP:Epidural Blood Patch):非透視もしくは透視下で、腰部や漏出が疑われる部位に自家血を注入し、髄液の漏れを塞ぐ方法。海外の情報では、初回成功率約85%、2回目でおおよそ90%改善、とされる。
・外科的手術の検討:ブラッドパッチで改善しない場合。静脈瘻に対する塞栓術もこのうちのひとつ。
こうした海外のプロトコルが国内学会で明確に共有されたのは、つい最近のこと。ブラッドパッチ以降の情報は限られていて、得にくいものでした。
私自身のこれまでの経過
前述の通り、この病名・原因に辿りつくには時間を要してしまうケースは少なくありません。私のケースも同様で、子供の頃からの体の症状の原因が長年分からないまま生活を送っていました。20代後半で「先天性変形性股関節症」であることが分かってからは、その関連痛や体のバランスがとりづらいことが原因で体調変動が生じるのかな、とも思っていました。
多岐にわたる症状のため様々な科を受診しましたが、原因はいつも分からず。内科的な検診はいつも異常なし。そんな中、2017年にこの病の存在を知っていた医師から検査を勧められ、脳脊髄液減少症と診断されました。
診断がついたこと自体、奇跡のように感じられました。ただ私の場合は、ブラッドパッチを受けても効果は一時的で、長くて1ヶ月半ほど。その後は元に戻ることを繰り返しました。
演奏家として本番に備えるため、5年間で9回のブラッドパッチを受けました。しかし最後の2回は何故か症状が悪化。その後はブラッドパッチを受けることは断念し、保存療法と代替療法、自分のこれまでの経験から得てきた対処方法でやりくりする生活を送っていました。
学会での出会いと新たな展開
”工夫をすれば、やれることもある”。そんな思いと対処方法の共有がお役に立てばと、3月の「日本脳脊髄漏出症学会2025」にて院長が私のケースを発表しました。そして、その発表の後お声がけくださったのが、第一人者のS先生でした。「まだ他に方法があるかもしれませんよ」。
気がつけば、なす術がないまま3年の月日が過ぎていましたので、思いがけない言葉に、光が差し込んだような気がしました。同時に、9回目のブラッドパッチ以降、QOLを落とした状態を受容しバランスをとる日々を送っていましたので、これ以上の加療をすることが逆に自然に抗うことのようにも、貪欲であるようにも感じられ、どう舵を切るべきなのか、少し考える時間が必要でした。
何かのために、誰かのためにと、放っておけば利他偏重的な思考の癖が芋蔓的に結論を導こうとします。でも今は、自分のことも同じくらい大切に扱える環境が私にはある。メリット、デメリットと共に、今の自分が大切にしている価値観に基づいて考えたとき、「もう一度、治療の道を辿ってみよう」と、心が定まりました。
この続きについて…
次回は、静脈瘻の検査体験について綴ります。
私にとって大きな転機となった体験を、具体的にお伝えできればと思います。