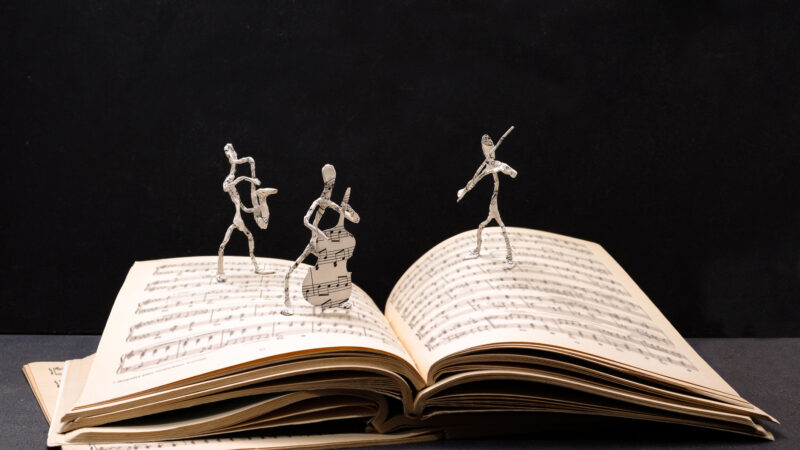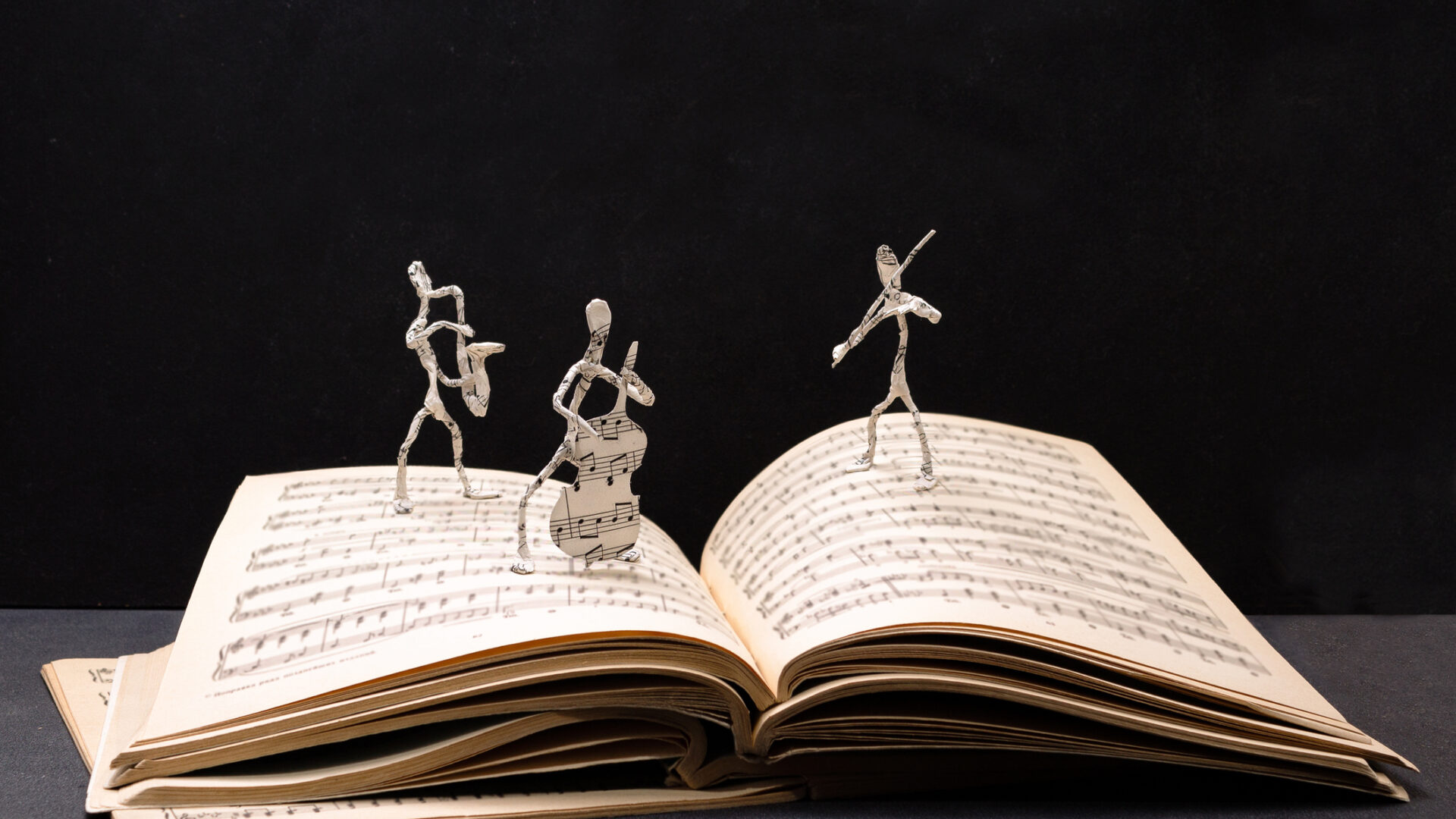
第79回全日本学生音楽コンクール東京大会予選審査
2025.09.16
東京オペラシティ・リサイタルホールにて行われました、毎日新聞社主催・NHK後援のコンクール、通称「毎日コンクール(毎コン)」の審査に参加いたしました。
前回の審査はコロナ禍より前のことでしたので、新鮮な3日間。久しぶりに学生さんの歌唱をたくさん聴かせていただきまして、最近の傾向、あるいは今回の傾向を感じる時間を過ごしました。
クラシックといえども、時代とともに変化する部分があります。
私たちの学生時代との大きな違いの一つは、やはりインターネットで気軽に演奏に触れられる環境の中で学んでいることではないでしょうか。逆に、生の舞台で、あるいは、お稽古場などで、演奏家の音を体に浴びる機会の頻度については変化があるのか無いのか、どなたか統計をとっていないかしら…と思いを巡らせました。
採点とともに、参加者全員に対しワンポイントアドバイスを書くのも、審査員の役割です。限られた時間、限られた文字数ではありますが、皆さんの次の一歩につながることを願いながら心を込めて書き続けました。
一番多く書いたワードとしては、「横隔膜」「legato」…でしょうか。
いずれも基礎的な要素ではありますが、これらをマスターすること、本番でも実行するには、やはり練習とともに舞台経験の積み重ねが必要です。ですから、練習の成果を思うように出せなかった…という学生さんも、自分に厳しい言葉を向けすぎないでくださいね。大切なのは、今回の経験を一つの成長の材料に変えて、淡々と訓練を続けられるかどうかです。「歌う」ということも、他の楽器と同様に、奏法の習得には時間のかかるものですから。
合わせて、「楽譜を読む」ということについて、学びを深めましょう。良い発声や自在な声はツールであってゴールではありません。後年に付け加えられた情報と、譜面の中に存在しているものを見極められると良いですね。
作曲家が残したものに向き合い、音に立ち上げる。
その媒体で在ること。
演奏家の仕事とは——
私の中では、こんな感じでした。
皆さんにとっては、どんなものですか?
その捉え方は一人ひとり異なるもの。そして、
それが音に現れてくるところがまた、音の不思議ですね。